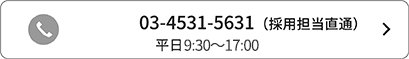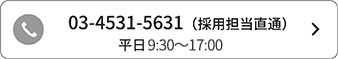「子どもと家族の生活にちょこっと色ときらきらを」ナンシーの療育研修レポート(3)
2021.06.02

「お子さん、親御さんの「やってみたい」を一緒に叶える」
そんなビジョンを掲げて、認定NPO法人フローレンスを母体とした「医療的ケアシッターナンシー」は発足しました。発足からおよそ1年半。医療的ケア児や障害児向けのシッターサービスを提供するなかで、医療的ケアに留まらず療育の観点にも向き合いたいとの思いから、外部講師を招いての療育研修が行われました。
講師としてお招きしたのは、発達コンサルタントの小島賢司さん。理学療法士として療育センターで働く傍ら、『HATTATSUコンサルタントのこじさん』として、発達運動学の知識を活かし、育児の不安や悩みに対してお子さん一人ひとりの個性に着目した最適な育児をご提案する活動をしています。
今回は全3回の研修最終日、第3回目の内容をご紹介します。
(第1回はこちら)
(第2回はこちら)
「ナンシーとして療育を提供するときに、何をもってナンシーらしい療育と定義していくか」
こちらをメインテーマに、第3回目の療育研修は始まりました。
私たちができる療育ってなんだろう
「地域に寄り添った看護がしたい。子どもやご家族にもっとじっくり寄り添いたい」とナンシーに飛び込んできた看護師。NICUなど病棟勤務が長いメンバーも多く、療育は初めての分野だったため、日々、目に見えない大きなものを追っているような気がしていたと言います。そんななかで、「私たちができる療育ってなんだろう」という部分を言語化し、自分たちが大切にするべきスローガンを決めることを目指して、全3回に渡る療育研修を行ってきました。
看護師一人ひとりのこれまでの経験と、これまでの研修で学んだ「療育」に対する知識をあわせて、点と点を大きな道にしていく最終回。
今回は以下の2つのテーマで、グループディスカッションに取り組みました。
①「看護師としての可能性と限界について」
②「私たちの療育とは何か?」
今回はディスカッションの内容と併せて、私たちが辿り着いたスローガンをご紹介できればと思います。

看護師としての可能性と限界について
まずはじめに、看護師としての可能性と限界について話し合いました。
限界については、課題がたくさん挙がりました。状態安定のための医療的ケアが多いと、どうしても「療育」という観点でご家族の期待に応えきれないことがあります。また、教育的な視点や躾の観点においては、どこまで対応すべきかの境目が難しいという点もありました。さらに、お子さんを楽しませつつ行動を促しながら、療育を実践する難しさもあります。限界を感じながらも、日々試行錯誤を続ける看護師。では、その限界を突破していくために、どんな場面で可能性を感じているのでしょうか。
可能性について話しはじめると、看護師の皆から「ご家族」や「子ども」という言葉がたくさん飛び出しました。例えば、親御さんの悩みを共有し、抱えている思いを軽減できたとき。また、なかなか多くの時間を遊びに割けない状態のなかでも、ご家族と相談しながら医療的ケアと並行して療育的な関わりができたとき。このように、ご家族や子どもに寄り添いながら何らかの状況を変えられたときに、看護師としての可能性を感じているとのこと。さらに、看護師持ち前の観察力やアセスメント力を生かすことで、お子さんの状態に合わせて活動内容を臨機応変に考えられるとの声も。
ご家族や子どもと接する日々のささやかな場面から、療育の可能性は広がっていくのかもしれません。話にあがった具体的な事例を一つご紹介します。ある看護師が、足を使ったボーリング遊びをする際、居間に敷いてあるマットレスの凹凸でピンが倒れてしまう環境だったため、マットレスの上に板や本を敷いて床を安定させてから行ったそうです。それをご家族にお話ししたところ、「そういう風にすればいいんだ!」とすごく喜んでくださったとのこと。このように、小さなことでもご家族が喜んでくれた経験を通して、「私たちが日々関わっている療育の内容を親御さんたちに提案する」それだけでも意味があるのではないか、と感じているといいます。
このように、看護師皆が具体的な事例を挙げながら、忌憚のない意見を活発に交わし合いました。それぞれが抱えてきた限界、可能性について臆することなく話し合うことで、共通した思いが少しずつ言語化されていきました。日々の訪問は一人で行いますが、ナンシーの療育はチームプレー。ディスカッションの様子から、チーム全体が信頼の元に成り立っていることが伺えました。

私たちの療育とは何か?
ナンシーとしてできる療育とは何か。自分たちが目指す方向性を探りながら、2度目のディスカッションが始まりました。1度目と同じく、様々な意見が飛び交います。そのなかでも、医療的ケアで状態を維持することをベースとして、子どもが楽しめる時間を作りたい。そこを主軸として、反応や表情などの細やかな変化に気づきたい、子どもの成長を親御さんと共有したいなど、看護師としての専門スキルを活かしつつ、子ども、ご家族にも寄り添いたいとの想いが多く語られました。
ナンシーの看護師が訪問するのは週に1、2回、2~3時間です。「子どもたちにとってはほんの少しの時間で、だからこそ楽しみな時間にしたい」と看護師は言います。ナンシーを利用している子どもたちは、普段は室内で座位で過ごしている場合がほとんどです。短い訪問時間のなかだけでも、外の世界に触れる遊びを通して子どもの可能性を広げたい。また、そこで生まれた余白時間をご家族の家事や外出に充ててもらうことで、レスパイトケアに繋がる側面も期待できます。
子どもたちは皆、大きな可能性を持っています。何かできることを見つけたら、それがまた次に繋がる。❝今❞の大切な時期に関わらせてもらえるというのは、実はすごいこと。
「今このときが将来に繋がっていくと思うと、わくわくしますね」
一人の看護師の言葉に、皆の笑顔が溢れました。
療育に向き合うなかで、前述したような「限界」を感じる場面、課題に向き合わざるを得ない瞬間もあるでしょう。しかし、看護師自身の「苦しい」気持ちは、子どもにも伝わってしまいます。自分たちの「可能性」を信じ、楽しみながら療育の時間を共有したい。ホッと息をつける、憩いの場でありたい。意見こそ様々ですが、看護師皆が向いている方向性は一つであると感じました。
ある看護師は、以前保育士に「その子の生活を豊かにしてあげたいと思う時点で保育だよ」と言われたそうです。それは療育にも通ずる部分があり、小さなところから生活を彩っていきたいと思いながら、日々看護や療育に向き合っているとのこと。例えば、「ご家族が忙しい時間でもナンシーの看護師がそばにいるから寂しくない」など、日常のちょっとした場面を支えるなかで生活にゆとりが生まれます。大きな変化よりも小さな日々の積み重ねを大切にしたい。丁寧に一人ひとりの子ども、ご家族と関わっているからこそ見えてくるもの、目指したいものが、そこにはありました。
小島さんは言います。
「お母さんが離れていても寂しくない。ご家族にその余白を提供できているんだと皆さんが知っていれば、「何もできていないのでは」という不安は軽減されるはずなんですね。「空白」も必要なことなんです。それはご家族を含めて互いの時間を確保できているということで、すごく大事だなと思うんです。」
子どもとご家族にとって、また、看護スタッフである自分たちにとっての最善を考えながら、話し合いは続けられました。お子さんやご家族に対する未来まで見据えた姿勢と眼差し、臆することのない自己開示を通して、より良い方向へと向かっていく。ディスカッションを通して、ナンシーというチームの強さをひしひしと感じました。

点と点が集まって、大きな道が見えてきた
ナンシーとして療育を提供する際に、何を持ってして「ナンシーらしい」と定義するのか。スローガンを設定するにあたり確認し合った、自分たちが目指す療育の方向性。互いの想いを実直に話し合うなかで飛び出した様々なキーワードを元に、「ナンシーらしい療育の定義」が決定しました。
「子どもと家族の生活にちょこっと色ときらきらを」
肩肘を張らず、気負い過ぎず、ご家族の日々の生活に彩りを添えていきたい。子ども、ご家族にとっての伴走者でありたい。そんな想いを込めて付けられたスローガンからは、温かな色が溢れています。ナンシーの核となるものが決まったことに、看護師皆から一様に安堵の表情が伺えました。
個人個人で違う「療育」に対する概念。しかしこうして指針ができたことにより、みんなが同じ想いでナンシーの療育が目指す方向性を伝えられるようになりました。
「この研修を通して、日頃から皆さんが一生懸命、療育に取り組んでいるという根底を感じました。何かに躓いたとき、とにかくみんなで話し合う時間は決して無駄ではないです。困ったらいつでも連絡ください。同じ日本にいて、子どもたちを守っている者同士、今後も一緒に頑張っていけたらと思います」
小島さんの力強い言葉に、看護師皆が大きく頷きました。
新しく決まったスローガンを掲げ、4月から迎え入れる新メンバーにも伝えていきたいと看護師は微笑みました。
「研修を終えた今、あったかい気持ちを抱いています」
研修序盤で小島さんが言った通り、みんなの点が集まって、大きな道が見えてきました。3ヶ月に渡る療育研修は、しっかりとした着地点を見つけたようです。
ナンシーでは現在、看護師を募集しています。
医療的なケアのあるお子さんとそのご家族の生活を彩り、少しでも支えていきたい。
「子どもと家族の生活にちょこっと色ときらきらを」
こちらの想いに共感された方は、ぜひ一度説明会に参加してみてはいかがでしょうか?
オンライン説明会に参加する
フローレンスの障害児保育・看護のお仕事に興味がある方はお気軽にご参加ください。服装自由・履歴書不要です!
直接応募する
説明会への参加がむずかしい方、「今すぐ働きたい」とお考えの方は、こちらから直接ご応募ください。

最新情報をお届けします!



説明会情報やスタッフへのインタビュー記事など最新のお知らせをLINEで配信しています。
お問合せ
ご不明点やご相談は、お電話またはフォームにてお気軽にご連絡ください。